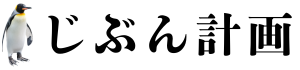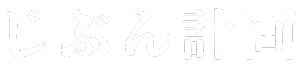「辞めたいわけじゃないけれど、このままでいいとも思えない」
「転職して後悔したらどうしよう。でも何も変えないのも怖い」
こんなふうに揺れる気持ちを抱える人は少なくありません。
でもそれは、決して優柔不断だからではありません。私たちの脳は、本能的に変化よりも現状を選ぶ傾向があるからです。
このような傾向は、心理学で「現状維持バイアス(status quo bias)」と呼ばれています。変化に伴う不確実性を回避し、慣れた環境にとどまろうとするのは、むしろ自然な心の働きなのです。
この記事では、その迷いを無理に振り払うのではなく、整理して言語化することで自分の判断軸を明確にする「5つの問い」をご紹介します。
1. このまま3年続けたら、自分はどう変わっている?
「今の仕事をこのまま続けたら、どんな未来が待っているか?」
この問いは、未来の自分をシミュレーションするための出発点です。
しかし、多くの人がこの問いに答えられないまま、「なんとなく今を続ける」ことを選んでしまいます。
それもそのはず。人は一般的に、自分の未来をリアルに想像するのが苦手です。
これは「未来自己の希薄化(temporal discounting)」と呼ばれる心理傾向で、将来の自分の感情や立場を「まるで他人事のように」感じてしまう現象です。
この心理的な壁を超えるためには、具体的な未来像を描いてみることが有効です。
たとえば次のような問いを書き出してみてください。
- 3年後の自分はどんな仕事をしている?
- スキルや収入、働き方はどうなっている?
- 今よりも充実していると言えそう?
- 「今の職場に残る選択」を続けたことで、得るものと失うものは何か?
こうした未来の自己像を想像することで、現在の延長線が「望む人生に向かっているのか」「足踏み状態なのか」がはっきりしてきます。
逆に、「未来の自分を想像したくない」と感じた場合は、それ自体が現状への違和感のサインかもしれません。。
2. 今の仕事は、自分の「強み」と「価値観」に合っている?
「この仕事、自分らしいって本当に言えるだろうか?」
これは、いまの仕事と「じぶん」の間にあるギャップを見極めるための問いです。職場でのストレスや違和感の多くは、「スキルのミスマッチ」や「価値観との不一致」によって生じています。
心理学では、こうした一致度を「自己一致(congruence)」と呼びます。自己一致が高いとき、人はやりがいや満足感を得やすく、逆にズレがあると、いくら待遇や肩書が良くても、心がすり減っていきます。
ここで振り返ってみてください。
- あなたの得意なことは、日々の仕事で活かされていますか?
- あなたが大切にしている価値観(たとえば自由・挑戦・安定)は、職場の文化と合っていますか?
- 仕事の成果が、誰かの役に立っている実感を持てていますか?
もしこれらの答えに自信が持てないなら、今の職場はあなたの成長と幸福に適した環境ではない可能性があります。
自分の特性を客観的に理解するには、ツールの活用も効果的です。
自分の強みを理解することは、転職を判断するうえでの「軸」を持つということ。その軸がブレなければ、どんな選択にも自信をもって進めるようになります。
ミイダスでは、自分の特性を手軽に確認できる無料のコンピテンシー診断が利用できます。
この診断では、職務適性やパーソナリティ、ストレスの感じやすさ、相性の良い上司・部下のタイプなど、ビジネスパーソンとしての特性が分かります。さらに、転職や年齢、学歴別に200万人以上の年収データをもとに、自分の年収を他の人と比較することもできます。
求人情報も企業が求めるスキルや経験が明確に設定されているので、自分に合った仕事を探せます。
3. 職場はあなたの「成長」を促してくれている?
「最近、自分が伸びていると感じたのはいつだろう?」
この問いは、今の職場が「あなたを育てる土壌」であるかどうかを判断する重要なヒントになります。
成長とは、単にスキルが増えることだけでなく、「挑戦できる機会」「意思決定に関わる余地」「評価される実感」など、心理的な栄養によっても支えられています。
もしあなたが……
- アイデアを出してもスルーされる
- 結果を出しても評価が曖昧
- 何をやっても上司の顔色次第
という状態にあるなら、それは個人の努力不足ではなく、「システムの問題」である可能性が高いです。
自分のせいではなく、環境があなたを消耗させている。
そう認識するだけでも、心は少し軽くなります。
職場を変えるには大きなエネルギーが必要ですが、まずは「異動や配置転換で環境を変えられるか」を探り、それが難しいなら「転職による環境改善」を前向きな選択肢として視野に入れてみましょう。
4. 経済的な不安が「選択の自由」を縛っていないか?
転職に迷いが生まれる理由のひとつに、「収入が減るかもしれない」という不安があります。この不安は無理もないものですし、軽視すべきではありません。
ただし、お金にまつわる判断では、「損を避けたい」という感情が意思決定に強く影響します。
これは「損失回避(loss aversion)」と呼ばれる人間の心理傾向で、得られる利益よりも、失う痛みの方を大きく感じてしまうのです。
たとえば、年収が下がる可能性があるだけで、本来なら魅力的な選択肢がすべて消えてしまう――そんな思考パターンに陥っていないでしょうか?
以下の問いで整理してみてください。
- 今の収入水準は、自分のスキルに見合っているか?
- 転職先での成長や可能性は、年収差を上回る価値になりそうか?
- 金銭面以外の満足(自由度、精神的な充実)はどう変化しそうか?
お金の問題は「不安」に見える部分を可視化すると、意外と整理できるものです。
クラウドワークスやココナラのように、スモールスタートで副業を始めてみるのも、有効なリスク分散になります。
5. 仕事が人生の「主役」になりすぎていないか?
「この働き方を、あと10年続けたいと思えるか?」
最後に問いかけたいのは、「仕事と人生のバランス」です。
どんなにやりがいのある仕事でも、それがすべてを圧迫してしまえば、幸福感は長続きしません。
有用なフレームワークとして、「PERMAモデル」という考え方があります。
これは、幸福感を構成する5つの要素[P: Positive emotion(前向きな感情), E: Engagement(社会との関わり), R: Relationships(人間関係), M: Meaning(意味), A: Achievement(達成)]を示したモデルで、仕事だけでなく、感情・人間関係・意味・達成感が調和することで、本質的なウェルビーイングが生まれるとされています。
つまり、「キャリア」だけを追いかけるのではなく、「人間としてのバランス」を見直すことも、転職か否かを考えるうえで欠かせません。
たとえば:
- 今の生活に、余白や遊びがありますか?
- 休日に心からリラックスできていますか?
- 健康や家族、人とのつながりは大切にできていますか?
働くことは、人生の一部であって、すべてではありません。
もし仕事が人生を占領しすぎているなら、それは見直すタイミングなのかもしれません。
最近では、柔軟な働き方を可能にする求人も増えており、リモート専門求人サイトでは、週4日勤務や完全在宅といった選択肢も広がっています。
最後に:迷いを「整理」することが、答えを生む
転職するか、今の仕事を続けるか。
その答えは、誰かが決めてくれるものではありません。
でも、「じぶんに問いを立てること」は、迷いを整理する最初のステップになります。
感情に流されるでもなく、理屈だけで割り切るのでもなく、「自分にとっての納得感」がある選択をすること。
それこそが、今の時代において最も信頼できる判断軸ではないでしょうか。
焦らず、でも止まりすぎず。5つの問いを手がかりに、あなたなりの答えを探してみてください。